記事公開日:2022/01/12
最終更新日:2023/11/16

業務改善は、企業の成長・拡大に欠かせないものです。たとえ順調に業績が伸びていたとしても、常に生産性やコスト、効率を見直して改善することが、成長・拡大の継続に繋がります。
賃貸仲介営業は不動産業の中にあって、比較的IT化が進んでいるジャンルではありますが、それでも不動産業全体がレガシーな業界であることは否定できない事実です。不動産業の営業現場以外で勤務したことがある人にはわかると思いますが、ファックスが営業に欠かせないというビジネスモデルは、他業種ではかなり考えられないという現実もあります。
しかし、業務改善というのは漠然としているため、何から手をつければいいのかわからないという担当者の方もいるかもしれません。ここでは、業務改善の進め方やポイント、注意点やフレームワークなどを紹介するので、わからない方はぜひ参考にしてみてください。
※下記の関連記事では人材育成を成功させるためのポイントやアイデアをまとめてます。業務改善によって教育する時間が作れた場合、こちらもチェックしてみてください。
目次
業務改善とは、業務の内容やフローにおける無駄や課題などの問題点を抽出し、対策を打ち出して実行することで、改善前よりも良い状態にしていくことをいいます。具体的には、業務の削減や効率化、経費削減、作業の負担を減らすシステム導入などが業務改善となります。
業務改善は1回で終わり、というものではないため、常により良い状態を保てるように続けていくことが重要です。
業務改善の必要性は、改善を検討している企業が抱える問題や成長目的によって異なります。たとえば、人材不足の解消や生産性の向上、働き方改革などに対して必要といえるでしょう。
現在、日本人口は減少傾向が続いており、特に若い労働力を確保するのが難しい状態です。適材適所で人材を配置するには、職場環境や労働環境を整えることが急務とされているため、業務改善が必要になるのです。優秀な人材を確保できれば、作業の効率も上がるので生産性向上も期待できます。
また、働き方改革も推進されていますが、業務がある限り改革は難しいこともあるでしょう。業務改善により、業務フローや業務内容を可視化することで無駄を省いたり、作業の順番を入れ替えたりできるので、業務プロセスを最適化し働き方改革も実践できるようになります。
業務改善は、部署内で生じる問題だけでなく、企業全体の問題解決にも繋がるので、経営上必ず行った方が良いことだといえるのです。

業務改善を行うことで得られるメリットは、4つ挙げられます。どのような業界であっても業務改善は必要であり、終わりのない作業です。しかし、とりわけレガシーでアナログな業界である不動産業界において、業務改善を行うメリットは非常に大きいといえます。
特に、以下で挙げたメリットを業務課題として認識されているのであれば、枝葉の問題よりもまずは幹の問題として、業務改善から着手されてみてはいかがでしょうか。
人材育成に必要な時間を削減したいと考えている企業であれば、人材育成にかかる時間のコストを削減できるといったメリットがあります。業務改善により、業務に不要なものを削減・標準化することで、業務のマニュアル化が簡単に行えます。マニュアル化を行うことで業務に携わりながら仕事を覚えられるので、時間をかけなくても人材育成が可能になるのです。
特に賃貸仲介業者においては、新人が習得しなければいけない業務内容やスキルが広範囲にわたります。業務のマニュアル化を行うことで、教育コストを大幅に減少させることが可能です。
金銭的コストの削減をめざしている企業であれば、経費削減のメリットを得られます。たとえば、資料やチラシなどを紙で作成している場合、これを改善してデジタル化をすることで、印刷代や紙代、郵送費や保管コストなどを削減できるのです。
また、業務の無駄を省いて効率化ができれば残業代の削減、業務内容を見直してテレワークが推進できれば交通費の削減、というように、あらゆるコストの削減に繋げることが可能です。
業務改善により経費と見えざるコストを減少させることで、業務の効率化が進みます。その結果、他社よりも早くスムーズに、お客様へ高品質なサービスを提供することが可能です。
「少々お待ちくださいませ」「ご連絡に2~3日お時間をいただきます」と、お客様をお待たせすることもありませんので、他社との差別化が図れるでしょう。
優秀な人材の離職・流出を止めたい場合、業務改善をして働きやすい環境を整えることができれば、離職率を低下させるメリットも得られます。無駄な作業が多く業務負担も大きい、人手不足で毎日残業しなければならない、など社員や従業員が不満を感じるような職場環境では、良い人材はどんどん離れていってしまうでしょう。
業務改善によって、無駄・不要な業務をスリム化したり、作業負担が減らせるシステムを導入したり、価値が感じられる仕事をしてもらえるように職場環境を整えれば、不満や不平を減らすことができます。働きやすい、もしくはやりがいのある職場であれば離職する人を大幅に減らすことができるので、人材確保に悩む企業にとって業務改善は大きなメリットといえるでしょう。
とりわけ賃貸仲介業界においては、人材の確保と教育は非常に重要な要素です。物件検索・提案・契約手続きなど、オフィスオートメーションは進みつつあります。しかし、反響対応、内見、契約は人が携わらないと、業務の遂行は不可能です。さらに、不動産業界はアナログでレガシーな業界であるため、お客様もアナログな人的対応を求めている一面もあります。無人化や完全機械化は理論上可能ですが、当面はまず不可能でしょう。1名の離職が会社の命運を左右する、小規模の仲介業者が多数存在しています。人材の確保と教育のためにも、業務改善は欠かせない作業といえるでしょう。
業務改善の必要性とメリットを不動産仲介業務に当てはめた場合、どのような効果があるのでしょうか。不動産仲介業務では、物件提案や内見以外にも書類作成や物件登録など、細かい事務作業があるため、業務負担の大きいことが課題となります。職場環境を整えることによる人材確保や、人材育成にかかる時間のコスト削減ができれば、営業の担当者は事務作業を事務員に任せることができるので、コア業務に集中できます。
また、お客様に向き合う時間も確保できるので、入念な来店準備や、より丁寧なヒアリングを行うことで、成約率のアップも狙えるでしょう。企業にとっても、顧客満足度や信頼性の向上が期待できるので、一石二鳥のメリットを得られるのです。
そのほかにも、人手不足による残業の負担が大きいと、その負担のせいで退職する従業員が増えてしまうということにも繋がります。そのため、働き方改革にも繋がる内容の見直しを行ったり、作業効率が向上するシステムを導入することによって、従業員の負担を大幅に軽減でき、退職のリスクを防ぐ効果も期待できます。

業務改善を効率よく進めるためには、手順をしっかり把握することがポイントです。ここでは、業務改善のプロセスを紹介するのでチェックしておきましょう。
まずは、現在抱えている問題点をすべて洗い出します。内容はざっくりでも良いので、「どの部署にどのような問題があるのか」「どの業務が非効率なのか」など、ミーティングや会議などで議論をしながら洗い出してください。業務改善は、問題を把握していないと意味がないので、洗い出しはとても重要なプロセスになります。
業務をすべて見える化する、というのは洗い出しの次に重要なプロセスです。いくら問題点が見つかっても、業務内容が可視化されなければ、解決策や改善点を見つけられません。
見える化は、業務の全体像を捉えるとともに、コストやフローを具体的に把握できるので、部署はもちろん企業にとってもメリットがあります。見える化は、業務を可視化するツールやフレームワークなどを活用すると、スムーズに進められます。
問題点の洗い出しと業務の見える化ができたら、次は課題と目標について、優先順位を含めて設定しましょう。課題とは、目標と現状の差を埋めるために行うことを指します。まずは、業務を効率化するための課題を複数設定し、どの目標から達成していくのか優先順位をつけてください。
また優先順位をつけると同時にKPI(重要業績評価指数)も設定しましょう。KPIとは、目標を達成するうえで、達成の度合いを計測するための指標であり、業務改善の効果を判断するための数字です。
たとえば不動産仲介業者であれば、賃貸物件の契約数をKPIに設定します。これが設定できていないと、業務改善の効果が検証できず、実行した施策が有効なのかどうかが把握できないので、KPIの設定は必ず行いましょう。
施策の計画とマニュアルを作成する事で、スムーズに業務を進める事が可能です。
計画・作成した内容は事前に上司に伝え、もし計画を変更、もしくはカスタマイズするのであればその旨をきちんと報告し、施策の結果に対する評価を正確に伝えられるようにしましょう。
施策が完了したら、業務改善効果が得られたのかどうかを、設定したKPIと照らし合わせながら評価・振り返りを行います。業務の効率化に成功したのか、無駄な残業を減らすことができたのかなど多角的に評価をして、効果が高いと判断できた施策はその後も現場に定着できるよう、継続して取り組むことが最善の方法です。
また、業務改善効果が得られなかったと判断された施策は、良かった点悪かった点などを振り返り、再度問題点を洗い出して、さらに改善を行うよう取り組みましょう。

業務改善のプロセスはそれほど難しくありませんが、実施をするうえでは注意点があります。また、思いがけない落とし穴もあるので、きちんと理解して業務改善を進めてください。
一番の注意点は、「現場がどういった問題を抱えているのかを把握できているか」ということです。業務改善では、問題点の洗い出しの際に現場の意見をヒアリングする必要があります。しかし、ヒアリングは幹部や管理職が行うことも多いため、一般社員や役職が下の社員の場合、心証を悪くしないように「問題はない」「業務はスムーズにまわっている」など、報告上よく見せようとすることがあります。
これを鵜のみにしてしまうと、問題の本質をつかめず、効果のある業務改善ができません。本音や現状の問題点を報告してもらうためには、現場の社員や担当者と信頼関係を結んでおくことが重要なので、良い関係作りを心掛けましょう。
業務改善では、意思疎通や理解が上層部だけでなく、現場まで落とし込まれているかを確認する必要があります。問題点は現場から吸い上げますが、どのように改善をしていけば良いか、施策を考えるのは上層部の仕事になります。そのため、業務改善に対する意思の疎通や理解が上層部だけでしか共有されていないことがあるのです。
実際に業務改善の施策を実践するのは現場なので、意思疎通や理解が共有できていなければ改善効果が得られません。改善を行う際には、上層部からしっかり現場に落とし込むことを忘れないようにしましょう。
施策期間と評価対象が短期間すぎると、改善の検証ができないので注意しましょう。業務改善は一朝一夕で達成できるものではありません。また、コストに関しても同じことがいえるので、長期的な目線が大切です。
短期間で効果を出したい、検証したいという気持ちもわかりますが、本気で業務改善を行うのであれば、適切な施策期間と評価対象を設けるようにしてください。
業務改善をするメリットが、企業だけでなく、従業員単位にも存在するかもしっかり考えましょう。たとえば、コスト削減は企業にとってメリットですが、従業員に直接的なメリットはありません。そのため、コスト削減の業務改善だけにフォーカスした施策では、従業員のモチベーションが上がらず、結果的に改善もスムーズに進まない可能性があります。
実際に施策を実践する従業員のモチベーションを上げることは、業務改善の効果を得るために必要です。そのため、業務フローの見直しやシステム導入による業務負担の軽減や効率化など、従業員のメリットもしっかり考慮して施策を考えましょう。
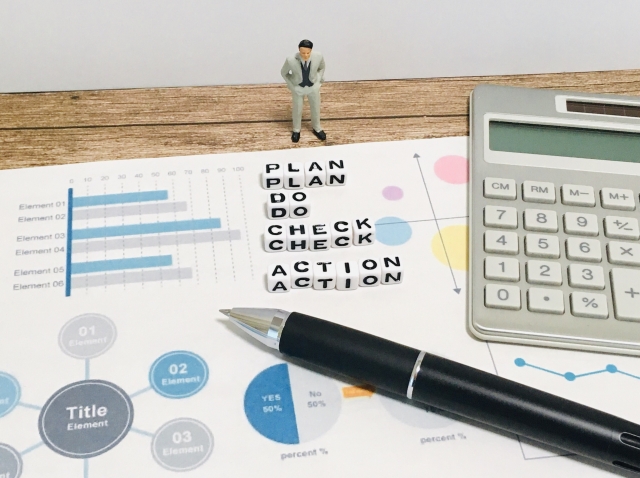
業務改善の際には、フレームワークをチェックしておきましょう。フレームワークは、改善を進めるときはもちろん、業務改善を提案したい場合でも利用できるので、役職に関係なく活用できます。
ここでは、業務改善におすすめのフレームワーク8選をご紹介します。
PDCAサイクルは、「Plan(計画)」「Do(実行)」「Check(評価・測定)」「Action(改善・対策)」という4つの検証型プロセスを繰り返すことで、目的や目標を達成できるフレームワークです。PDCAサイクルのプロセスは、一見特に真新しいものではなく、普段の業務でできているようなイメージがあるかもしれません。
しかし、従業員一人ひとりが設定された目標を計画に基づいて実行し、その結果について検証するプロセスを徹底することで、計画を継続すればいいのか、さらに改善が必要なのかなどを的確に分析できます。
QCDは、「Quality(品質)」「Cost(コスト)」「Delivery(納期)」の頭文字を取った言葉で、生産管理で重視される3つの要素を表しています。またQCDの派生語であるQCDFのFは「Flexibility(柔軟性)」のことで、主に製造業やサービス業で使われており、QCDSのSは「Safety(安全)」のことで、こちらは主に建設業界で使用されています。
QCDのフレームワークは、業務の無駄を減らして生産性をアップさせるために活用するのが一般的です。仕事の「求められるクオリティ」を意識し、「どの程度のコストをかけられるか」を計算し、「いつまでに納品(完了)させるべきか」を決めて、納品(完了)後の結果を分析します。プロジェクトごとにQCDを活用することで、結果が出る業務の進め方を身につけられます。
ECRS(イクルス)は、「Eliminate(排除)」「Combine(統合)」「Rearrange(順序変更)」「Simplify(簡素化)」の頭文字を取った言葉で、業務改善の「順番」とそれを進める「視点」を見直すフレームワークのことです。
「Eliminate(排除)」では不要な業務やルールがないかを分析し、「Combine(統合)」ではまとめられる業務がないかを分析します。さらに「Rearrange(順序変更)」は作業の順序変更や、業務内容を再度整理して効率化できないかを分析し、「Simplify(簡素化)」は業務が複雑化していないか、効率化できないかを分析します。
これらのワークによって業務フローを全体的に見直すことで、業務の効率化・スリム化を実現し、コストや時間の余裕を生み出すという業務改善を実現できるのです。
BPMNは「Business Process Modeling Notation」の略語です。アメリカのOMGによって国際標準に定められているビジネスプロセスモデリング表記法になります。
BPMNは、業務工程のフローや担当者などを図形化して、矢印などを使って可視化し、課題点や問題点を発見するフレームワークです。可視化するためのモデル図に使う描画記号は種類が多く、フローの作成工程は少し複雑です。しかし、誰でも理解しやすい業務フローを作ることで、業務の流れがスムーズになります。
業務が滞りやすい場合、BPMNを使えば簡単に滞っている箇所を見つけられるので、原因をすぐに分析できます。
KPTは、「Keep(継続)」「Problem(問題)」「Try(トライ)」の頭文字を取った言葉です。つまり、「業務の振り返り」を書き出して、業務改善を行っていくフレームワークのことを指します。
「Keep(継続)」は成功したことや今後も続けた方が良いこと、「Problem(問題)」は失敗したことや止めた方が良いことを意味します。「Try(トライ)」は「Keep(継続)」と「Problem(問題)」を踏まえたうえでの改善策や新たに実行していくべきことを書き出しましょう。
社員がそれぞれのKPTを書き出して可視化することで、本人だけでなく周りの人間と業務内容を共有し、良い点や悪い点をしっかり分析できるのが、このワークのメリットです。
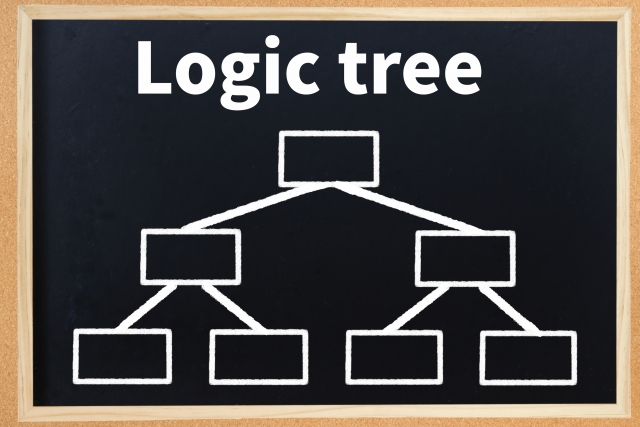
ロジックツリーは、ツリー(樹形図)を使って、特定の問題の原因を論理的に分解していくフレームワークです。トラブルや問題が起こった場合、その原因を追及しなければ同じ失敗を繰り返すことになります。
ロジックツリーでは、一つのワードから派生するワードを順番に挙げていき、一つひとつのワードを論理的に分析しながら問題の原因を掘り下げていきます。ツリー状に書き出すことで、原因と関係性のある事項が漏れたり、重複したりすることなく深く追求できるというのが特徴です。
また、このワークではひとつの問題を解決するだけではなく、掘り下げた際に、新たに浮上する問題点も発見できるので、効率よく業務改善ができます。
バリューチェーン分析は、開発や生産、マーケティング、アフターサービスなど業態に関わるすべての業務を機能ごとに細分化し、どの機能(工程)で価値が生み出されるのかを分析するフレームワークです。サービスや商品が顧客に届くまでのプロセスを可視化し、どの活動が自社の強みになっているのか、どの活動にどれだけのコストがかかっているかなども分析します。
バリューチェーン分析では、強みと問題点を把握することで業務の改善点を洗いあぶり出せますが、同時に事業戦略にも役立てることが可能となっており、あらゆる業態で活用されています。
マンダラートは、多くのアイデアを出したいときに活用するフレームワークです。3×3の9マスの紙を用意し、中央にテーマを書いて、放射線状に広がる周囲8マスに関連ワードを書いていくことでアイデアを発想していくという、シンプルなワークになります。
8マスを埋めたら、最初の9マスの周囲をさらに3×3の9マスで囲み、最初に書いた関連ワードを元にさらにアイデアを発想することで大量のアイデアを生み出せます。
業務改善のもたらすメリットや方法を理解し、いざ業務改善に着手しようとしても、どこから着手して良いのかわからなくなりがちです。そこで、賃貸仲介業で役立つ業務改善ポイントをご紹介します。
不動産業界にも、DXの波は着実に押し寄せてきています。少なくとも、事務的な分野や集計などの分野におけるアナログな作業では、競合他社との競争に勝ち残れないでしょう。
以下のようなポイントが、アナログ作業として業務改善の対象になります。解決策もご提案しておりますので、参考程度にご確認ください。
| アナログ作業内容 | 導入システム | 解決 |
| 複数ポータルサイトへの入稿作業を、個別に手作業で行っている | 物件管理システム | 一括入稿を行う |
| 申込受付に手書きの申込書を使用している | 電子申込へ移行する | |
| 顧客管理が紙ベース顧客管理が属人化 | 顧客管理システム | システムで一元管理顧客育成の進捗が誰でも確認可能 |
毎日あたりまえのように行っている業務は、改善の余地がないものとして認識してしまいがちです。しかし、ルーティン業務も業務改善の対象になります。
| ルーティン作業内容 | 導入システム | 解決方法 |
| 業務日報の作成・報告 | 日報管理システム | 作成業務負荷の軽減 |
| 不在時受電の取次がノートや付箋に記入している | グループウェアチャットツール | 紙ベースの管理からシステムでの管理に移行 |
| 勤怠管理が自己申告やタイムカード | 勤怠管理システム | 勤怠管理をシステム管理に移行残業時間や有休管理も可能 |
昨今はKGIやKPIが重視されており、データやその元となる数字の集計に追われることも多くなってきました。正確なデータをスムーズに集計して管理することは、業務改善の一丁目一番地といえるでしょう。
| データ管理内容 | 導入システム | 解決方法 |
| 反響・来店・成約各件数の集計 | 顧客管理システム | 各種件数の集計が自動化個人別や媒体別の集計も可能来店率や成約率も自動集計 |
| お客様の各種メール開封件数や開封時間など | 開封率や開封時間・デバイスなどを自動集計追客の効率化や追客の効果的な時間設定が可能に | |
| 車両運行日誌 | 社用車運行システム | 移動ルートや運転時間の集計管理私的など不正利用の排除にも |
一連の業務フローの中で、意外と業務改善として見落としがちなのは二重作業です。複眼でチェックすることも重要ですが、単純作業の二重化は論外といえるでしょう。
| 重複しがちな作業 | 対応 | 解決方法 |
| 行動予定の重複※同じ方面に別の担当者が赴くなど | 行動予定の確認 | 朝礼などで行動予定を確認同じ方面で誰が対応しても良い業務は一人にまとめる |
| 業務の重複※同じ物件の写真撮影を2回行うなど | 業務精度の向上業務履歴の確認 | 社内フォルダの整理し登録ルールを統一二重作業になっていないかを事前確認するほか、二重作業にならないように業務の漏れをなくす |
それでは、業務改善の実績として、著者が実際に行った業務改善とその効果をご紹介します。
業務改善で細かいことを考えたり、会議を行ったりする前に、まずは大掃除をしてください。無駄なものを容赦なく捨ててしまいましょう。そして、これでもかというくらいに整理整頓をします。整理整頓は「トイレットペーパーのストックはここ」という場所を決めるレベルではいけません。同じ用途のファイルであれば色や材質をすべて統一し、ラベルの書き方や記載情報も完全にルール化します。個人情報が保管されているラックは、すべて施錠可能なものに変更しましょう。
社員のパソコンや共有フォルダも、整理整頓対象です。個人情報のあるファイルはデスクトップに置かず、共有フォルダに格納します。共有フォルダ内のフォルダ作成も、ある程度は自由で良いですが、物件名は大文字小文字、アルファベット表記かカタカナ表記かをルール化しましょう。
重要なことは、綺麗であることや整理されていることではなく、会社が業務改善に本気で取り組むという姿勢を見せることにあります。また、保管や格納のルールを統一することで、社員が勝手にルールを作るのを防止することが可能です。こういった社員の独自ルールがいつの間にか慣習になり、円滑な業務の妨げになることを理解しましょう。
業務日報や数値の集計は、システムを導入してほぼ自動化させました。なぜなら、社員に業務の妨げになっているものは何かを聞いたとき、多くの社員が「内向きの仕事が多い」という不満を口にしていたからです。
一方でマネジメント側からすると、データ集計は重要な作業です。そこで、システムを導入して報告業務と集計業務をスリム化することにより、現場の営業担当者とマネジメント側で対立する課題を解決しました。
データ集計がリアルタイムで共有・確認できるようになりましたので、社内会議の頻度を減らしました。営業担当者の会議出席回数は、多くても月に1度です。
朝礼は確認事項をまとめ、10分程度まで時間を短縮させました。行動予定や休暇スケジュールは、すべて共有システム(顧客管理システムやグループウェアシステムのスケジュールを活用)に登録することを徹底しています。ここでも、営業担当者の報告ストレスと、マネジメント側の管理ストレスを同時に軽減させています。また、お客様の予定により都合が合わないため、業務終了後の終礼は廃止しました。ルール変更や共有すべき事案は、すべてグループウェアなどで周知することに統一しています。
一方で営業担当者には、必ず各種ポータルサイトや、顧客管理システムのカスタマーサクセスとの定例会議に参加させるようにしました。そもそもカスタマーサクセスとの定例会議がない状態であり、あったとしてもマネジメント側がお茶を濁すような顔合わせに終始していたため、この状態では機能不全と判断したのです。カスタマーサクセスは、多くの会社の多様なデータを保有しています。営業担当者やマネジメント側でも原因がわからず、数字の浮き沈みや市場の動向をかなり早い段階で察知していることがほとんどです。
このような旬な情報に触れさせる機会を多く設けることで、自ら考える力を営業担当者に与え、業務品質の向上に役立てました。ポータルサイトへ掲載する物件の選定や、掲載後の閲覧・反響状況に目がいくようになり、営業担当者が根拠と戦略に基づいた集客マーケティングに参加するようになっています。
システムをベースにした業務に慣れてくると、残業の多いイメージのある賃貸仲介業であっても、閑散期はほぼ全員が定時に退社することが実現します。著者は残業には否定的ですが、システム稼働により、空いた時間を業務品質の向上に充てることが重要です。
主に以下のようなことに時間を費やし、業務品質をさらに向上させました。
以前は会場に赴き参加していたセミナーなども、現在はウェビナーと称して、パソコンから気楽に参加できます。システムやアプリの制作会社が主催する無料の業務関連セミナーが多数存在していますので、気になるものがあれば、自由に参加するように指示しました。
写真撮影のコツ・ポータルサイトのコメント登録のツボ・接客応対マニュアルなど、賃貸仲介営業に役立つものが多数ありますので、ぜひ参加してみてください。
トラブルが発生したり、数字が急に下がったりしたとき、思いついたように社員研修やロープレを行いますが、意外と長続きしません。営業品質を維持向上させるために、社員教育やロープレの場を定期的に設けました。
追客は、賃貸仲介営業でも重要な業務の一つです。しかし、多忙だったり気持ちが落ち込んでいたりすると、真っ先に手を抜いてしまいがちな業務でもあります。
顧客管理システムありきの話にはなりますが、追客状況を確認したうえで、追客に力を入れるようにしました。架電回数や時間帯、メール文章の推敲、返信がなければSMSの送信など、できることはたくさんあります。単に「追客しろ」だけでは、営業担当者のモチベーションは下がる一方です。しかし、データを元に方法論や選択肢を一緒に考えることで、「やらされている感」がかなり減少したように思います。
※空いた時間で下記4本の関連記事もチェックしてみてください。
賃貸仲介営業店舗は、おおむね18時から19時までの営業がほとんどです。しかし、お客様のお仕事の都合などで、20時にアポイントということもしばしばあります。また、追客を行うにあたり、業務時間終了後の着電率が高いことがデータからわかってきました。
これらの状況から、思い切って時差出勤制度や半休制度、テレワーク制度、直行直帰制度を導入しました。承認は必要としながらも、営業担当者が自ら予定や出勤スタイルを選択できるようにしたのです。
多様な出勤制度は、求人において効果が抜群で、導入後は離職者も激減しました。自宅にいながら重要事項説明をしたり、ポータルサイトへの物件登録をしたり、歯医者に行ってから出勤したりと、ワークライフバランスが社員にとって重要なことが身に染みてわかりました。
最後に、業務改善を行うにあたってよくある疑問や質問にお答えします。言い方を変えれば、このような疑問や質問は、課題の本質であるともいえるのではないでしょうか。また、業務改善を行うにあたってのお悩みも盛り込んでいますので、ぜひお読みください。
業務改善が効率化や生産性の向上を目的としたものであるのに対して、経費削減は販管費の削減を目的としたものです。
業務改善の結果として効率化が図られ、生産性が向上し、その結果として人員の削減や不要な間接経費が圧縮されることにより、経費が削減されるという副産物を得ることはありえるでしょう。一方、経費削減は経費を削減することのみを目的としたものであり、その狙いに違いがあることは明白です。
経費削減も企業においては重要な施策ですが、むやみな経費削減はすべきではありません。経費には、目に見えるコストと目に見えないコストが存在しています。目に見えるコストとは、損益計算書に記載できる、文字通りレシートや領収書が存在するコストのことです。目に見えないコストとは、労働力や教育コスト、作業に要する時間などのことをいいます。目に見えるコストを削減した結果、目に見えないコストが増大してしまった場合、これは経費削減といえるでしょうか?著者は、経費削減できたとは評価できないと考えます。
現在は、DXによる効率化や生産性の向上が謳われています。なぜ効率や生産性が重要なのかといえば、コンプライアンスやライフワークバランスを重視する労働者が増加したため、労働力を確保するために企業が行うべき必要な施策だからです。経費削減は、業務改善を行うことにより結果的に得られることがありますので、順番としては業務改善を優先すべきでしょう。
各社の状況にもよりますが、軽微な範囲であれば、独自の判断で進めても差支えないと考えます。しかし、必ず上司や同僚に、事前の報告や共有は怠らないようにしましょう。
また、昨今はシステムの導入により、業務改善を図ることも少なくありません。お金がかかる場合は、必ず上司や会社の決済を経てから行うようにしてください。
新しいものに対して、アレルギー反応が生じるのが人間の特性です。新しい業務フローやルールを構築しても昔の状態に戻るときは、チェック機能が不足しているか、組織への業務改善内容やマインドが周知されていないかの、どちらかの可能性を疑うべきでしょう。
本来は自主的に是正されることが望ましいですが、困難なときはチェック体制を強化してみてはどうでしょうか。また、業務改善に関する項目を評価に盛り込むのも、一つの方法です。
部署間で、業務改善に温度差が生じることはよくあることです。このような場合は、役割を決めてしまうのが良いでしょう。
このように役割を明確にすることで、業務改善はスムーズに進められます。

業務改善というのは、生産性を高めることが一番のポイントです。作業の効率化やシステム化、コスト削減などの改善策は、すべて生産性のアップに繋がることなので、一つずつ丁寧に取り組んでいきましょう。また、賃貸仲介業などの小さい組織であればあるほど、業務改善は目に見えた成果を生むことができ、効果も実感しやすいでしょう。
何から始めればいいのかわからない、迷ってしまうという場合は、紹介したフレームワークや業務改善の実例を活用して業務改善の一歩を踏み出してみてください。最初は効果の見えないような小さな改善でも、積み上げていくことで将来的に生産性を大きく変えられる可能性があるので、フェーズに適した業務改善を実践していきましょう。
記事へのコメント | |