記事公開日:2022/06/09
最終更新日:2024/01/11
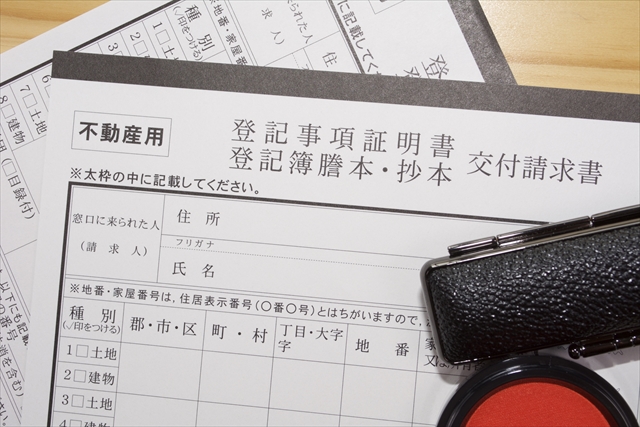
不動産取引を完了した後に行うのが不動産登記で、これには建物を建てた場所や所有者、債権者などの詳細情報が記載されています。不動産登記の申請は義務ではないものの、不動産登記が登録されていないと不動産に関する情報がわからず、何らかのトラブルに発展するおそれがあります。
そんな不動産取引は、オンラインで手軽に申請することが可能です。今回は、不動産登記の申請方法やオンライン申請の流れについて解説していきますので、不動産登記に興味を持っている方はぜひチェックしてみてください。
目次
不動産登記の申請方法は主に以下の3つです。
それぞれの方法を理解して、自分に合った方法で登記申請を行いましょう。
不動産登記の窓口申請は、法務局の窓口で行います。窓口申請は、登記申請日当日に受理されるため、完了までの日数が短いのがメリットです。また、不動産登記に自信がない人は法務局で相談に乗ってもらうことも可能なので、登記相談が必要な人は事前に法務局で予約を行いましょう。
ただし、法務局の窓口は平日の8時30分から17時15分までしか開いていません。スケジュールの調整が難しい他、近くに法務局のない場合、移動にかかる時間・コストが大きいのもデメリットといえます。
| 費用 | 600円 |
| 対応時間 | 平日8:30〜17:15 |
| 受理までの時間 | 当日中 |
法務局に直接訪れるのが難しい場合は、登記申請書類一式を法務局に郵送して申請することも可能です。近くに法務局がない人でも手軽に申請ができるため、時間に縛られる心配はありません。
ただし、申請書類が法務局に届いて受理されるまでに時間がかかります。申請後に修正があった場合や取り下げたい場合に、対応が難しいというデメリットがあることを覚えておきましょう。また、窓口申請の費用にプラスして郵送代がかかるので、3つの申請方法の中で一番費用がかかる申請方法といわれてます。
| 費用 | 600円+郵送代 |
| 対応時間 | いつでも |
| 受理までの時間 | 1〜2営業日後 |
以前は窓口・郵送の2つしか申請方法がありませんでしたが、2008年からオンライン申請が可能になりました。オンライン申請なら窓口や郵便局に行く必要はなく、自宅に居ながら登記申請ができます。
窓口申請と同じく、法務局の業務時間内に申請すればその日に受理されるのがメリットです。進捗状況をオンライン上で確認することもできるので、いつ完了するのか不安に思うこともなくなります。
便利なオンライン申請ですが、誰でも気軽に申請できるわけではありません。オンライン申請には専用ソフトや電子署名、電子証明書などが必要で、申請を行う前に環境を整えておく必要があります。これらが用意できないと、添付書類は窓口か郵送のどちらかで提出しなければいけません。
| 受け取りが窓口の場合 | 受け取りが郵送の場合 | |
| 費用 | 480円 | 500円 |
| 対応時間 | 平日8:30〜21:00 | |
| 受理までの時間 | 平日8:30〜17:15/当日中上記以外/翌営業日 |
3つある不動産登記の申請方法のうち、オンライン申請には4つのメリットがあります。申請方法にお悩みの人は、オンライン申請のメリットを理解したうえで検討しましょう。
オンラインからの不動産登記申請は、パソコンやスマートフォンを使って事務所や自宅から簡単に行えます。わざわざ法務局や郵便局に行く手間がかからない他、手書きする必要もないので、業務の空き時間や移動中に申請することも可能です。
前述のとおり、窓口申請のデメリットは場所と時間が限られることです。一方、オンライン申請は場所と時間を気にする必要がないので、自分の都合が良いときに不動産登記が行えます。
先ほどご説明した申請費用を比較すると、以下のとおりです。
| 窓口申請 | 郵送申請 | オンライン申請 |
| 600円 | 600円+郵送代 | 480円(窓口受け取りの場合)500円(郵送受け取りの場合) |
オンライン申請は、他の申請方法と比べると100〜120円ほど安く済ませることができます。地方に住んでいる方にとって、郵送代がかからない点は大きなメリットといえます。もちろん、法務局や郵便局に行くための交通費もかかりません。
オンライン申請の受付時間は、窓口申請と比較すると以下のように異なります。
| 窓口申請の受付時間 | オンライン申請の受付時間 |
| 平日8:30〜17:15 | 平日8:30〜21:00 |
オンライン申請の受付時間の方が少々長いため、仕事が終わった後に申請する方も少なくありません。ただしオンライン申請であっても、当日中に受理してほしい人は窓口申請の受付時間である平日の8時30分から17時15分までに申請する必要があります。
不動産登記をオンラインで申請すると、登記情報提供サービスというサイトで登記情報が閲覧できます。窓口・郵送申請の場合は登記情報の確認に書類の発行が必要ですが、登記情報提供サービスを活用すればそのような手間がかかりません。
登記情報提供サービスでの登記情報閲覧は無料で行えますが、他のサービスを利用するには費用が発生するため注意が必要です。また、登記情報提供サービスの無料閲覧には法的効力がありません。印刷しても使用することはできず、内容の閲覧に限られます。

不動産登記のオンライン申請は、3ステップで簡単に行えます。それぞれの内容を覚えて、トラブルなくオンライン申請を完了させましょう。
不動産登記には、主に以下の書類が必要です。
登記の内容により必要書類が変わるため、事前に調べたうえで確実な書類を準備しましょう。また、これらの添付書類の提出には電子署名や電子証明書が必要です。用意が難しい人は、添付書類をオンラインではなく窓口か郵送で提出する必要があります。
オンラインで登記申請書を作成するには、申請用総合ソフトを利用する必要があります。申請用総合ソフトは、登記・供託オンライン申請システムのホームページからダウンロードすることが可能です。
申請用総合ソフトがダウンロードできたら、どの種類の登記申請書を作成するかを選びましょう。法務省のホームページに記載例や作成例が載っているため、それらを参考にすれば書類の作成がスムーズに進みます。
出典:「登記・供託オンライン申請システムとは」(法務省)
参考:法務省 「商業・法人登記のオンライン申請について」
すべての記載が完了したら、申請データを送信します。平日の8時30分から17時15分に送信すると、送信日当日に受理されます。オンライン申請では、窓口・郵送のどちらかの交付方法を選ぶことができ、それぞれ費用が異なるため、自分に合った方法を検討しましょう。
不動産登記はオンラインで申請できますが、5つのポイントに注意しなければいけません。オンラインでの申請を検討している人は、ここから解説していくポイントを把握しておきましょう。
登記簿謄本や登記事項証明書が不動産関係で必要な場合は、正式な書類を発行する必要があります。たとえば登記情報提供サービスで無料閲覧できる内容を印刷しても、正式な書類として使用できないため注意しましょう。
オンライン申請が受理されても、すぐに交付できるとは限りません。受け取り方法を郵送にした場合は1~3日ほどかかるため、できるだけ早く手に入れたい方は窓口で受け取るようにしましょう。
ただし窓口で受け取る場合であっても、時間によっては翌日交付が叶わないこともあります。緊急で書類をそろえなければならない場合には、早い時間に窓口で直接申請してもらうのがおすすめです。
不動産登記のオンライン申請には、以下の環境が求められます。
| CPU | 800MHz以上推奨 |
| メモリ | 1GB以上推奨 |
| ディスプレイサイズ | 1024×768以上推奨 |
| OS | Windows 8.1の場合:Internet Explorer 11Windows 10の場合:Internet Explorer 11、Google Chrome |
| バージョン | iPhoneの場合:14.1Androidの場合:10 |
| ブラウザ | iPhoneの場合:SafariAndroidの場合:Google Chrome |
Macの場合、パソコンからオンライン申請できません。また、バージョンが上記より古い場合はアップデートが必要です。
オンライン申請には、申請者IDを取得する必要があります。登記・供託オンライン申請システムのホームページのトップページから申請者情報登録ボタンを押し、申請者IDとパスワードを登録しましょう。この申請者IDは任意のもので構いません。
申請者情報の仮登録が完了したら、登録したメールアドレス宛に確認メールが届きます。メールの認証ボタンを押すと、申請者IDの取得が完了します。申請者IDとパスワードはログイン時に必ず必要なため、忘れないようにメモを取っておきましょう。
オンライン申請には、正確な住所が求められます。これは省略することができないため、事前に正式な住所がわかるものを準備しておきましょう。
また、申請には登記登録されている住所が必要です。不動産の所在地と間違える方も多いので、記載ミスがないように注意しましょう。

窓口・郵送・オンラインの3つから申請できる不動産登記は、気軽に利用できるオンライン申請が便利です。不動産登記のオンライン申請には、4つのメリットと5つの注意点があります。
外出自粛による影響もあり、オンライン申請の需要は今後増えると予想されています。しかし、インターネットに慣れていない、あるいは利用環境が用意できない場合、各種手続きが進まなくなる可能性があります。今回ご紹介したメリットや注意点の内容を理解したうえで、便利なオンライン申請を検討しましょう。
記事へのコメント | |